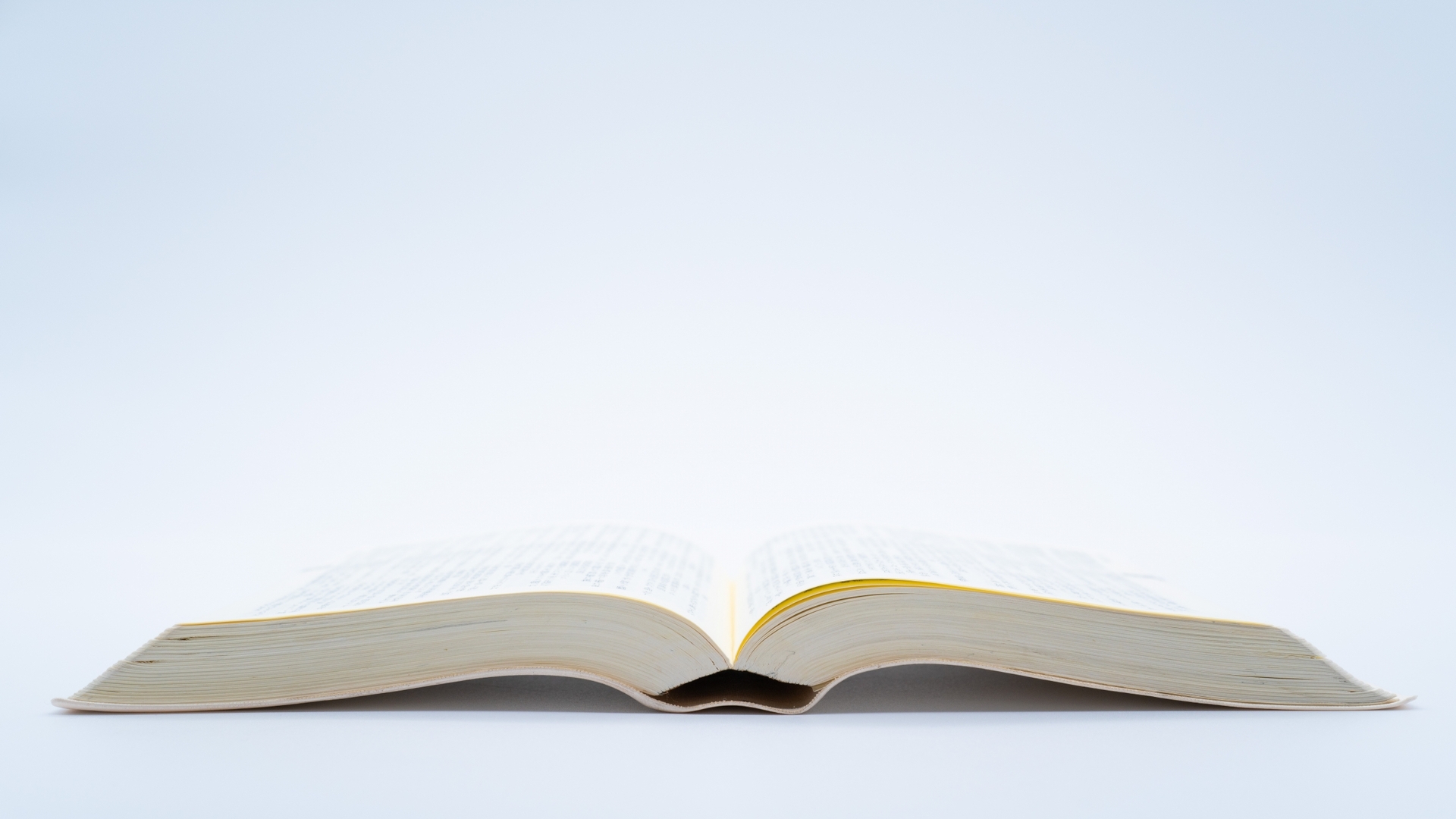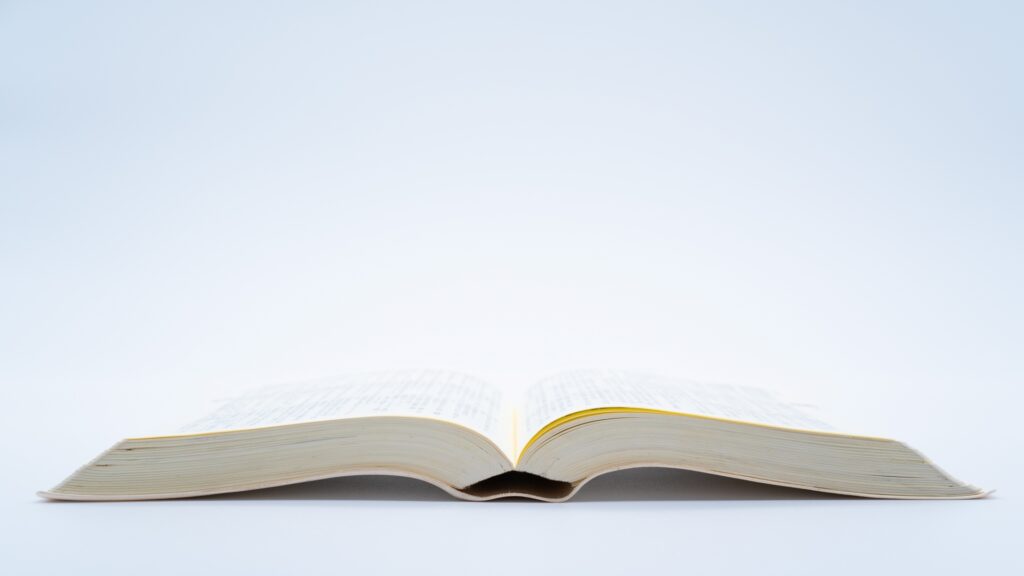
ここでは、告訴・告発や告訴状に関連する用語を一覧でまとめています。
各用語について、よりくわしく知れる解説ページへのリンクも載せているので、ぜひ併せてチェックしてみてください。
告訴・告訴状に関連する用語集
告訴
被害者やその他法律で定められている一定の立場の人が、捜査機関へ犯罪事実を申告し、犯人の処罰を求める手続きのこと。
告発
犯罪の被害者本人や犯人はでない第三者が、捜査機関に犯罪事実を申告して犯人への処罰を求める手続きのこと。
告訴状
告訴の手続きに必要となる書面。本来、口頭のみでも告訴は可能だが、事実関係や処罰意思を明確にするために告訴状を提出するのが一般的。
被害届
警察をはじめとした捜査機関に、犯罪被害を受けた事実を申告するための書類。被害届の提出によって事件が起きた事実が捜査機関に把握され、捜査開始の端緒となる。
被疑者
捜査機関から犯罪の疑いをかけられて捜査対象になっている者で、まだ起訴はされていない者のこと。
民事事件
個人対個人や企業対企業、個人対企業の紛争の解決や、損害賠償請求などを求めて裁判所に提起されたもの。民事調停や民事訴訟、労働審判、支払督促、保護命令など、さまざまな手続きがある。
刑事事件
犯罪行為をしたことが疑われる者について、国の捜査機関が介入して捜査を行い、裁判において刑罰を科すかどうか等について判断を行う手続きのこと。
告訴権者
犯人の処罰を求めて犯罪事実を申告する「告訴」において、それを行う権利(告訴権)を有する者のこと。原則として、犯罪の被害者本人またはその法定代理人。
告訴不可分の原則
ひとつの犯罪事実のうち一部に対してなされた告訴や、共犯のうちの一人または数人に対する告訴は、犯罪事実の全部や全共犯者にその効力が及ぶという原則。告訴の取り下げについても同様。
起訴
犯罪事実を把握した検察官が、被疑者への刑罰を求めて裁判所に訴えを起こす手続きのこと。
親告罪
告訴権者による告訴がなければ、検察官が公訴を提起(起訴)することができない犯罪のこと。
非親告罪
告訴がなされなくても起訴可能な犯罪のこと。親告罪として規定されていない犯罪はすべてこの非親告罪にあたる。
内容証明
一般書留郵便物の内容について、郵便局が証明する郵便サービス。差出人のほか、受付日や郵便物の内容、宛先等の項目を残せる。
公訴
検察官が裁判所に対して、被疑者を刑事裁判にかけることを求める申立てのこと。
控訴
第一審判決について不服を申し立てる手続きのこと。日本では「三審制」が採用されており、控訴審は第二審にあたる。
上告
第二審(控訴審)の判決に対して不服を申し立てる手続きのこと。法律の適用に誤りがある場合や判決に重大な瑕疵があると考えられる場合などに行われる。
告訴・告発センター
警察本部や各警察署に設置されている、告訴・告発に関する情報提供や相談、受理の手続き等を行っている窓口。
委任状
自ら行うべき手続きを他人に代行してもらう際に、その手続きが本人の意思にもとづくものであることを証明するための書類。
逮捕
被疑者の逃亡や証拠隠滅を防ぐために、身柄を拘束する刑事手続きのこと。警察署の中にある留置所に収監され、最長で48時間、身柄を拘束される。
→逮捕されたくない!逮捕を回避するための有効な対処法はある?
勾留
逮捕後に行われる長期の身柄拘束のこと。勾留請求が認められると、最大で20日間拘束される可能性がある(被疑者勾留の期間)。
示談
裁判ではなく、当事者同士の話し合いにより解決を図る手段。あくまで民事上の解決手段であるが、刑事手続き・処分に大きな影響を与えることも少なくない。
→示談は刑事事件においてなぜ重要?告訴取り下げなどメリットを解説!
逆告訴
法律用語ではないため明確な概念があるわけではないが、“自分が告訴された場合に、その告訴を行った人を逆に「虚偽告訴罪」で告訴し返す行為”を逆告訴と呼ぶことがある。
刑事罰
刑罰法規及び刑事訴訟法が適用される刑事手続を経て有罪判決が確定した場合に執行される不利益処分。